※このコラムは「雑談が苦手で、会話が続かない人」のための“話のネタ帳”です。
読むだけで、ちょっと話してみたくなる雑談ネタをストックできます。
こんにちは、カブラブログの管理人・カブラです。
今日は、家の前にこっそり埋まってる“ばってん印”の話から、
「ブランドとは何か?」というテーマを考えてみたいと思います。
【結論(この記事でわかること)】
家の前の歩道にある“ばってん印”を見たことがありますか?
それは、ただの印じゃありません。
境界杭は、「価値」や「ブランド」の正体を教えてくれます。
この記事では、
- 境界杭が“動かしてはいけない”理由と、その社会的意味
- 同じモノなのに、ランクやネーミングで価値が変わる不思議
- 境界杭に学ぶ、“ブランド”が生まれる仕組み
…を通して、
「本質を見抜く力」を育てるヒント をお届けします。
ちなみに、こういう日常の違和感や思考のタネは、
Audible
でエッセイや思考系の本を1冊聴いておくだけでも、自然と増えていきます。
【話ネタ本文】
土地の境界を示す“境界杭“
このあいだ、家の前の歩道を何気なく見ていたら──
あったんです。
“❌(ばってん)”みたいなマークがついたコンクリートのブロック。
アスファルトの端っこに、ひっそり埋まっていて、
目立たないけど、確かにそこにある。
あれ、なんだろう?って思って調べてみたら、
「境界杭(きょうかいくい)」っていうらしいですね。
土地の境界──つまり「ここからここまでがうちの敷地ですよ」っていう、
目印なんだそうです。
注意!立派な犯罪です
でも、ちょっと思いません?
「じゃあ、これ動かしたら、自分の土地、広くなるんじゃない?」って。
……わかります、僕も思いました(笑)。
でもダメなんですって。
境界杭を勝手に動かすと、「器物損壊罪」っていう立派な犯罪になるらしいです。
え、杭をちょっとずらしただけで“犯罪”?
いやいや、そんな大げさな……って思ったけど。
それだけ「境界」って大事なものなんですね。
“杭”社会の階層構造
で、さらに調べてみてビックリしたのが、
あの杭には「ランク」があるってこと。
最上位は「日本経緯度原点」っていう名前からして強そうなやつ。
そこから、1〜4等の基準点があって、
僕たちの足元に埋まっているのは、最下位の“個別境界杭”。
つまり──
あの“ばってんマーク”は、ピラミッドの一番下っ端。
でもね、名前に“原点”とか“1等”とかつくだけで、
なんだか価値あるように感じませんか?
僕、ちょっと「最上位の杭、見に行ってみたいな」って思いましたもん。
ランク付けと価値
これって──
ブランディングの話に、そっくりじゃないですか?
本質は同じ「杭」なのに、
ネーミングとランクづけで、価値の感じ方がまるで変わる。
「この境界杭は“日本経緯度原点”です」って言われたら、
なんか崇高な感じがするし、SNSで映えそうだし(笑)。
でも中身は、ただの測量用の杭です。
ブランドって、物の本質よりも、
「どう語られるか」「どう名付けられるか」で価値が決まってしまう。
境界杭が、教えてくれました。
本質を見ていますか?
僕たちはつい、名前や見た目で判断してしまうけど、
それって、どこまで“本質”を見てるんでしょうね。
- Apple製だから優れている?
- ハイブランドだからオシャレ?
- 有名大学だからすごい人?
そう思い込んでいるだけかもしれません。
あなたの足元にも、何気ない“ばってん”が埋まっていませんか?
もしかしたらそこに、“大切なヒント”が隠れてるかもしれませんよ。
【話ネタに使えるポイント】
- 「家の前に、❌マークがあるんですけど…あれ、境界杭って言うらしいですね」と軽く切り出せる
- 「実はあれ、勝手に動かすと犯罪なんですよ」と雑学としても盛り上がる
- 「最上位の杭は“日本経緯度原点”って言うんですよ」と豆知識っぽく披露できる
キーワードは
“名前や格付けで価値が変わる”と“ランク付けはブランディング”
ちょっと知的な話題にも展開可能なネタです。
ちなみに、こういう日常の違和感や思考のタネは、
Audible
でエッセイや思考系の本を1冊聴いておくだけでも、自然と増えていきます。
【「本質を見抜く力」を育てる3つのヒント】
「じゃあ、どうすれば“名前や格付け”に惑わされずに、本質を見抜けるのか?」
そんなふうに思った方へ、僕なりの3つのヒントをまとめてみました。
- 「なんでそう思った?」と自分に聞く
名前やブランドで「すごい」と感じたときに、
「なぜそう思ったのか?」と自分に問いかけてみましょう。
理由を言葉にできないときほど、それは“思い込み”かもしれません。 - 見た目より「中身」で判断するクセをつける
かっこいい名前、キラキラした見た目──
それだけで判断しないように。
「何に使われている?」「どんな働きをしている?」という“役割”に注目すると、価値の本質が見えてきます。 - 「一番下の杭」にも意味があると知る
最下位の“ばってん杭”にだって、大事な役目があります。
上か下かで価値を決めるのではなく、「どれも必要な存在」と思うと、見え方が変わってきます。
あなたが最近、ちょっとモヤモヤした“評価”や“格付け”。
それって、少し見方を変えるだけで、もっとフェアに見えるかもしれません。
👉 あわせて読みたい
【回転寿司】回らなくなっても残った価値|“形”を捨てた進化の話
【記事まとめ】
- 家の前にある“ばってん印”は、土地の境界を示す大事な杭
- 境界杭にはランクがあり、価値を感じるのは「ネーミング」の力
- ブランディングは、“本質”よりも“語り方”で価値が変わる世界
- 僕らの価値判断は、意外と「名前」に影響されている
【最後に】
普段、何気なく見ていた道ばたの“ばってん”。
そこに、ブランドや価値のヒントが隠れていたとは思いませんでした。
“境界杭”、ちょっと見直してしまいそうです。
……とはいえ、最上位の杭、やっぱり気になりますけどね(笑)。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

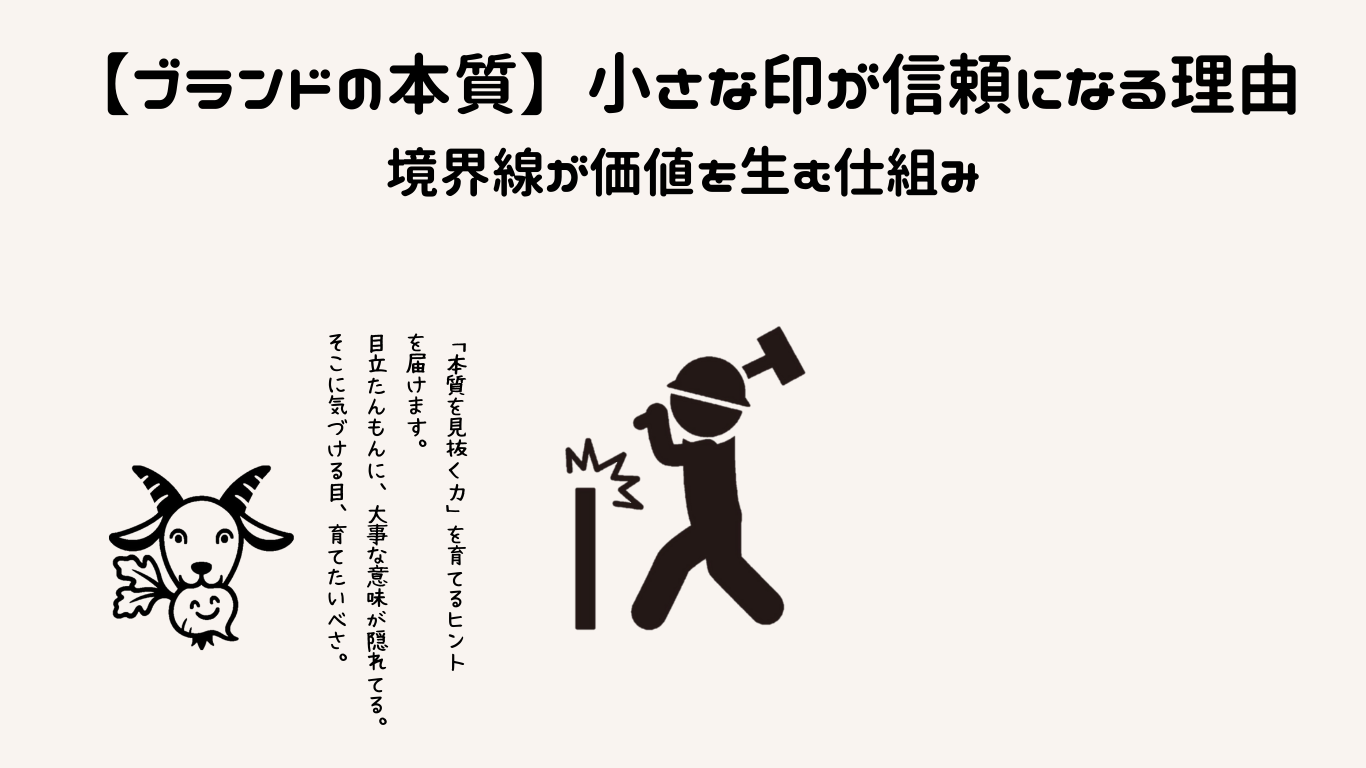
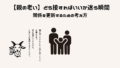

コメント