お葬式や、ちょっと気まずい場面で、どう声をかければいいか迷うことってありますよね。
正しいことを言ってるはずなのに、相手の心が閉じてしまう…。
そんな時に思い出してほしいのが、この“説得しない説得”の話です。
僕が叔母のお葬式で目にした、小さなやりとりから、“寄り添い”で心を動かすヒントが見えてきました。
“伝わる接し方”について考えるきっかけにもなる、ひとつ仕込んでおきたい話ネタです。
※このコラムは「雑談が苦手で、会話が続かない人」のための“話のネタ帳”です。
読むだけで、ちょっと話してみたくなる雑談ネタをストックできます。
【結論(この記事でわかること)】
このエピソードが教えてくれたのは、
“正しさ”を押し出すよりも、相手の心に寄り添う方が人を動かせる、ということ。
お葬式の場面でも、職場の会議でも、どちらが正しいかを決める必要はありません。
代わりに、「ああ、この人は今こういう気持ちなんだな」と受け止める。
それが、関係を壊さずに続ける唯一の方法かもしれません。
次にお葬式や気まずい場面の話をする機会があれば、このネタをそっと忍ばせてみてください。
ちなみに、こういう日常の違和感や思考のタネは、
Audible
でエッセイや思考系の本を1冊聴いておくだけでも、自然と増えていきます。
【話ネタ本文】
こんにちは、カブラブログの管理人・カブラです。
今日は、叔母のお葬式で見た、ちょっと不思議で、ちょっとあったかい出来事についてのお話です。
正しさや説得よりも、大切なことって、きっとこういうことなんだろうなぁ…と思った出来事でした。
淡々とした一日、のはずが
今日、叔母のお葬式に行ってきました。
とはいえ、故人とはそこまで親しくはなかったので、
行事として淡々と参加していた感じです。
こういう場って、親戚が久しぶりに顔を合わせる機会でもあるんですよね。
でもまぁ、特にドラマも起きないだろうな…と思っていたんです。
あの出来事が起こるまでは。
“帰る”と言い張る叔母
納棺が終わって、通夜までの空き時間。
親戚一同で控室にいたのですが、
そこにいたもう一人の叔母(ちょっと認知が始まってる)が突然言い出したんです。
「そろそろ帰るわ」
…いやいやいや。
今あなた、葬儀会場ですやん。
みんなで「いや、今日は泊まりですよ」と説得するも、本人はもう完全に“帰るモード”。
その場の空気がちょっとピリつきはじめたとき、思いがけない人物が立ち上がりました。
まさかの救世主は、あの叔父
立ち上がったのは、82歳になる喪主──つまり叔母の旦那さんです。
僕が子供の頃から、あまり話さないタイプで、ちょっと怖い印象だった叔父。
でもその日、彼は穏やかに、ゆっくりと、叔母の前に座りました。
そして静かにこう言ったんです。
「故人は最後、話すこともできなかったから…あなたがこうして話せているのが、うらやましいです。
もう少し、あなたのお話、聞かせてもらえますか?」
説得しない説得
その瞬間、場の空気が変わりました。
さっきまで「帰る!」と一点張りだった叔母が、表情をふわっと緩めて。
そのあと、二人で5分ほど静かに話して。
最後には、叔母がこう言ったんです。
「お話できてよかった。ありがとうね」
驚きました。
正直、状況がちゃんと見えてないと思っていたのに、相手に感謝を伝えるなんて。
“心が動く瞬間”って?
このやりとりを見て思ったんです。
「人の心って、“正しさ”では動かないんだな」って。
説得でもなく、怒るでもなく、無理に引き止めるでもなく、
ただただ“あなたを大事に思っています”という姿勢で、目の前の人と向き合う。
きっと叔母の中にも、帰りたい理由や不安があった。
でもそれを否定されず、受け止められたことで、初めて安心できたんだと思います。
あなたはどうですか?
誰かと向き合うとき、“正しさ”ばかりで話していませんか?
本当に必要なのは、案外「正論」じゃなくて、「寄り添い」なのかもしれません。
【話ネタに使えるポイント】
- 「お葬式って、親戚の再会の場にもなるんですよね〜」と切り出せる
- 「人って、正しさじゃ動かないんだなって思った話があって…」と語れる
- 「静かに寄り添うって、最強の説得かも」と、ちょっと深い雑談にも発展
キーワードは、
“説得しない説得”と、“寄り添いの力”。
あったかさと驚きのあるエピソードで、雑談にもピッタリです。
ちなみに、こういう日常の違和感や思考のタネは、
Audible
でエッセイや思考系の本を1冊聴いておくだけでも、自然と増えていきます。
【“寄り添い”で心を動かす3つのヒント】
「じゃあ、どうすれば”寄り添い”で気持ちが伝わるのか?」
そんなふうに思った方へ、僕なりの3つのヒントをまとめてみました。
- “正す”より“聞く”を選ぶ
つい相手の間違いを正したくなるけれど、実は多くの場合、それは本人もわかっていたりします。
まずは「そう思ったんだね」と言ってみる。
それだけで、心のドアは少し開きます。 - “相手の背景”に目を向ける
今の言動だけを見るとおかしくても、
その人の不安や混乱、過去の経験を想像すると、見方が変わります。
「何があったんだろう?」と想像することで、自然と寄り添う姿勢が生まれます。 - “答える”より“寄りそう”を心がける
何かを解決しようとするより、
「そばにいるよ」「話を聞くよ」というスタンスが人の安心になります。
行動より“在り方”が伝わるとき、相手の心も動き始めます。
あなたが最近モヤモヤした“あのやりとり”。
それって、もしかしたら「正す場面」じゃなくて「寄り添うチャンス」だったのかもしれません。
👉 あわせて読みたい
【親の老い】どう接すればいいか迷う瞬間|関係を更新するための考え方
【記事まとめ】
- 葬式は、家族や親戚が“再会”する場でもある
- 認知症の叔母に、寡黙な叔父がかけた一言が、心を動かした
- 正しさや理論で説得するより、気持ちに寄り添うことが人を動かす
- 「寄り添う姿勢」は、最強のコミュニケーションかもしれない
【最後に】
人を動かすのは、「正しさ」じゃない。
…って、よく聞くけど、今日その意味がちょっとわかった気がしました。
説得じゃなくて、寄り添い。
押しつけじゃなくて、傾聴。
おじちゃん、渋すぎです。
正直、今日いちばんカッコよかったの、喪主だったなと思います。(笑)
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

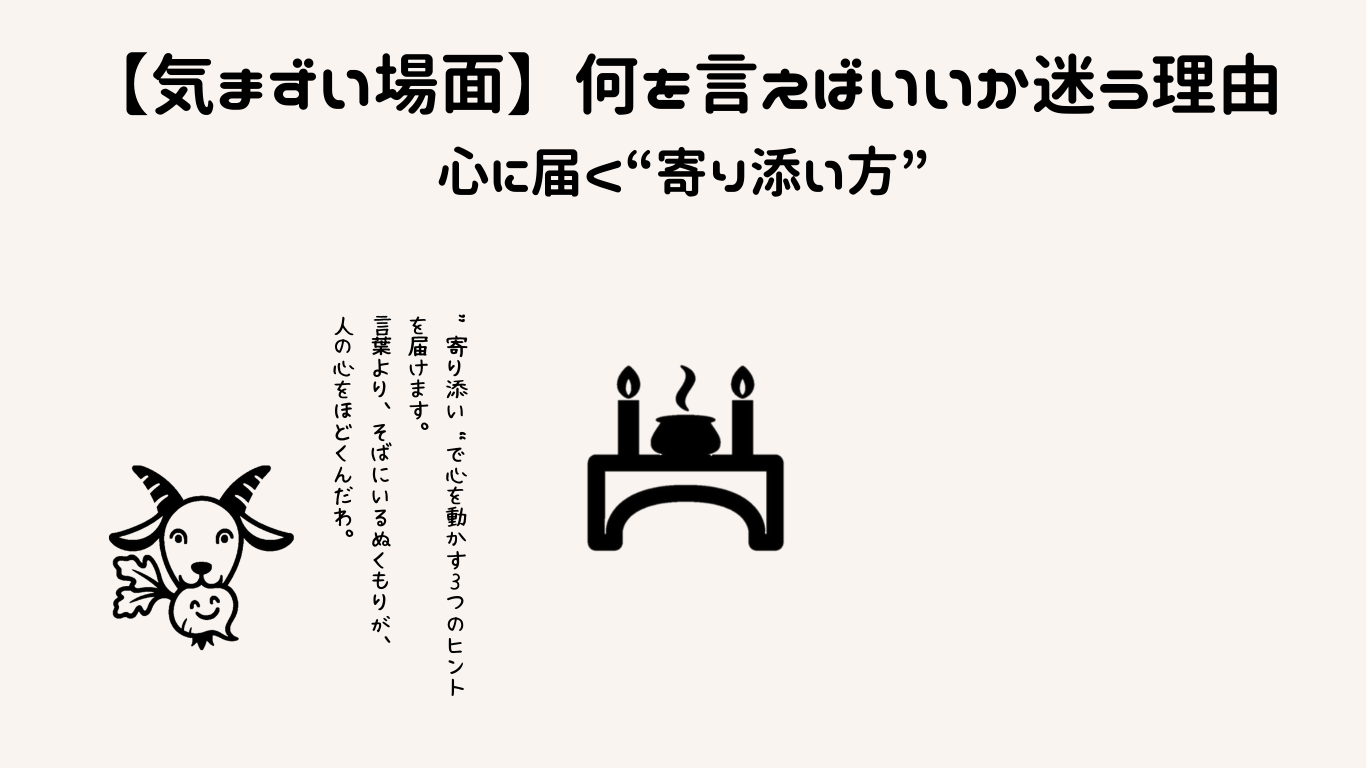

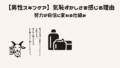
コメント