懇親会や会社の集まりで、「ちゃんと話さなきゃ」と気を張ってしまうことってありますよね。
誰も悪くないのに、自分だけ浮いている気がして疲れてしまう…。
そんな場面で思い出してほしいのが、この“出席確認だけで成立する懇親会”の話です。
僕が実際に経験した立食パーティーの違和感から、
「無理に盛り上げなくても価値は果たされている」というヒントが見えてきました。
“ただいるだけの役割”について考えるきっかけにもなる、ひとつ仕込んでおきたい話ネタです。
※このコラムは「雑談が苦手で、会話が続かない人」のための“話のネタ帳”です。
読むだけで、ちょっと話してみたくなる雑談ネタをストックできます。
【結論(この記事でわかること)】
このエピソードが教えてくれたのは、
「懇親会で成果を出す」よりも、“そこにいる価値”を理解する方が関係を守れる 、ということ。
会社の集まりでも、付き合いのパーティーでも、
無理に盛り上げ役を引き受ける必要はありません。
代わりに、
「ここは“話す場”じゃなくて“出席する場”なんだな」
と受け止めるだけで、心の負担は大きく減ります。
次に懇親会の話題になったときは、
この“出席するだけ価値”のネタをそっと忍ばせてみてください。
ちなみに、こういう日常の違和感や思考のタネは、
Audible(30日間無料体験)
でエッセイや思考系の本を1冊聴いておくだけでも自然と磨かれていきます。通勤時間が、コミュニケーションの仕込み時間に変わります。
【話ネタ本文】
こんにちは、カブラブログの管理人・カブラです。
先日、会社の大きな会合がありまして。発表会と立食パーティーの“フルコース”。
「これ……一体、誰が楽しんでるんだ?」と心の中でツッコミつつ、
お皿を持ったままウロウロしていたときに気づいた、
懇親会って実は“出席確認”なのかもというお話です。
“苦手なパーティー”で見えた景色
会社の会合って、だいたいホテルの宴会場じゃないですか。
で、各部署の発表が2〜3時間続き、最後に“お約束”の立食パーティー。
……正直に言います。
僕、立食パーティー、苦手なんですよね。
広い会場に100人以上。料理は豪華っぽいんだけど、立ちながら落ち着かないし、
結局は仲のいい同僚と円卓を囲んで、いつも通りの会話をして終わる。
「これ、懇親してなくない?」
と毎回思うんです。
なぜか落ち着かないあの時間
名刺交換もするし、社外の人にも挨拶はするんですよ?
ただ、そこから深い話にはならない。
むしろ、
“知り合い以外と長く話しすぎないように気を使ってる自分”
に気づいてしまって、さらに疲れる。
そもそも、懇親会って
「話して仲良くなる場」なのか?
それとも
「話してる風に見せる場」なのか?
気づけばそんな疑問が頭をぐるぐるしていました。
会社トップの“静かな存在感”
ところがその時、ふと視界に入ったんです。
会社トップが、立ち位置的にはめちゃくちゃ目立つ場所にいるのに、
ほとんど誰とも長くしゃべっていない。
淡々と、料理をつまみ、
淡々と、周囲を見回し、
淡々と、そこに“いる”。
「あ、この人も楽しんではいないな……」
そう思った瞬間、妙に納得したんですよね。
懇親会の本質は「出席していること」
気づいたんです。
懇親会って、
“社交の場”じゃなくて、“出席の場”なんだと。
・来ている
・見ている
・その場を共有している
これだけで、会社に対して
「はい、私はここにいます」
という存在証明になっている。
つまり――
無理に盛り上がらなくても、役目は果たしているのかもしれない。
あれだけ目立っていた会社トップでさえ、
「話してナンボ」ではなく、
「いるだけで成立していた」んだから。
あなたにとっての“ただいるだけ価値”は?
あなたはどうですか?
パーティーや集まりで、
「もっと話さなきゃ」「もっと人脈を…」
と気負ってしまうタイプですか?
でも、もしかしたら――
“そこにいる”という行為自体に価値がある場って、意外と多いのかもしれません。
学校のホームルーム、
家族の集まり、
友だちとの飲み会。
あなたが最近、「ただいるだけ」で救われた場は、どこでしたか?
【話ネタに使えるポイント】
- 「懇親会って、実は“出席確認”なんじゃないかと思ったんですよ」と切り出すと、共感されやすい
- 「会社トップもあんまり楽しそうじゃないですよね?」と続けると、軽い笑いになる
- 「無理に社交しなくても、ただ“いる”だけで役割果たしてる気がしません?」と問いかければ、深い話に展開可能
キーワードは、
“存在証明”と“ただいる価値”。
ビジネスシーンの定番イベントを、優しく再定義できる話ネタです。
ちなみに、こういう日常の違和感や思考のタネは、
Audible(30日間無料体験)
でエッセイや思考系の本を1冊聴いておくだけでも自然と磨かれていきます。通勤時間が、コミュニケーションの仕込み時間に変わります。
【“懇親会のしんどさ”を減らす3つのヒント】
「じゃあ、どうすれば懇親会で疲れずに済むのか?」
そんなふうに思った方へ、僕なりの3つのヒントをまとめてみました。
- “役割は出席”と決めておく
懇親会の目的を「人脈づくり」ではなく、「存在を示す場」と捉えておくだけで、気負いがスッと消えます。
事前に“今日は出席が役割”と自分に許可を出しておくと、気持ちの揺れが大幅に減ります。 - “長居しない会話”をデフォルトにする
無理に盛り上げようとするから疲れる。
むしろトップ層ほど「短く話して、短く離れる」が基本動作です。
「軽い挨拶 → 30秒で退出」を自分の標準にすると、場の流れの中で自然に見えます。 - 安心できる“帰れる場所”を一つ持つ
同僚・知り合い・料理テーブルなど、自分が戻れる“基地”をひとつ設定しておくと、心理的にかなりラク。
社交の場が苦手でも、「戻れる場所」を確保しておけば消耗が最小限になります。
あなたが最近しんどかった集まり。
それって、ちょっと視点を変えるだけで、もっと軽やかに参加できるのかもしれません。
👉 あわせて読みたい
【職場の気まずさ】沈黙が怖くなる理由|関係を深める受け止め方
【記事まとめ】
- 立食パーティーは、意外と多くの人が苦手
- 上司や会社トップも「楽しんでるわけではない」ケースが多い
- 懇親会の本質は「話すこと」より「出席すること」
- “ただいる価値”は、会社以外の場にも応用できる
【最後に】
僕はずっと、懇親会に対して
「もっと話さなきゃ」と身構えていたんです。
でも、トップでさえ一人で料理をつまんでいる姿を見たとき、
「あ、別に気負う必要ないんだ」と、ふっと肩の力が抜けました。
……というわけで次回からの懇親会は、
堂々と“ただいるだけスタイル”でいこうと思います。(笑)
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

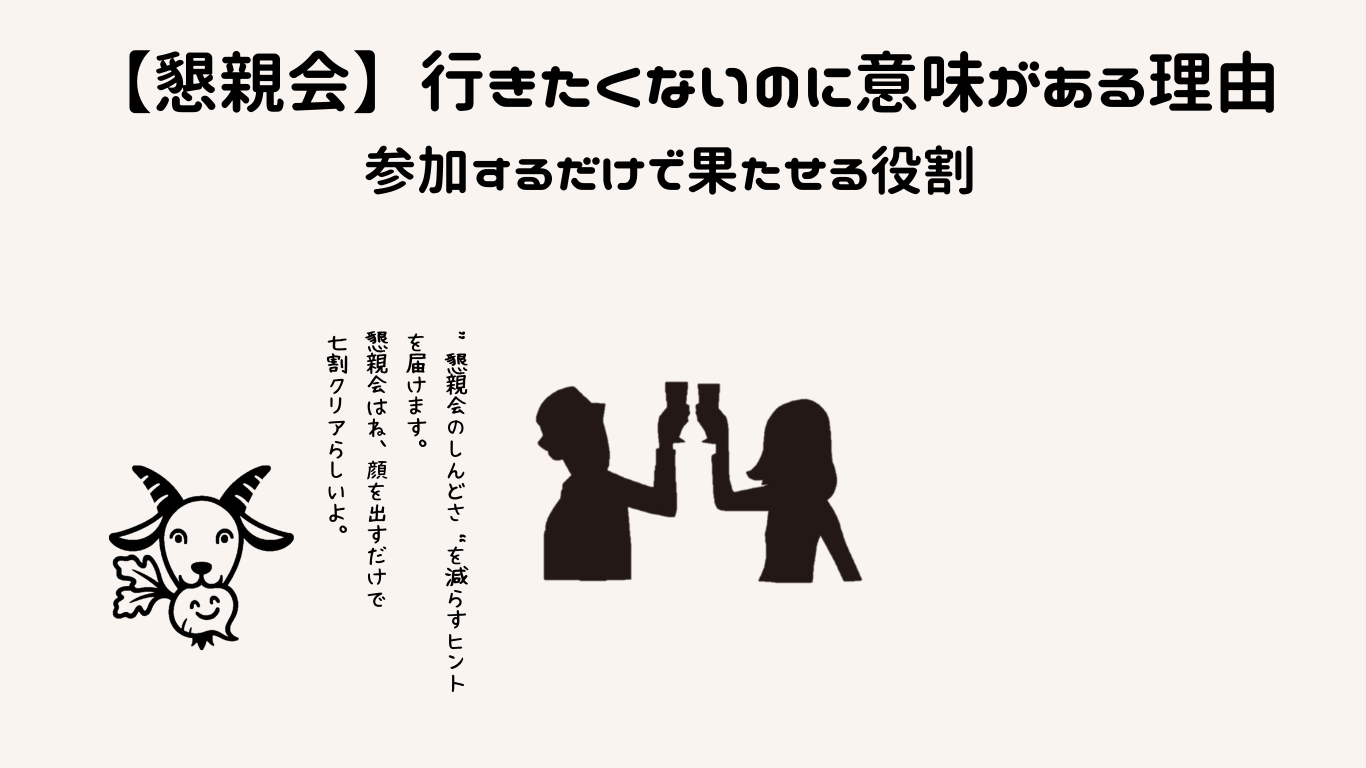
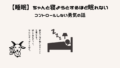

コメント